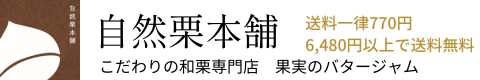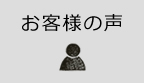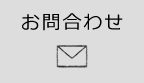栗屋大賞2019 エッセイ部門入賞作品
作品1.「仇討ち?!」 杉江 正子 (新潟県)
母と妹と私、3人とも栗が大好きだ。女性が好むものとして「芋栗南京」という言葉があるくらいだから、母娘そろって栗好きが珍しくはないだろうが、私達の栗に対する思いは単なる「好き」とは少し違う気がする。
栗○○、マロン○○、という物に出会うと3人はピクリと反応する。まるで長年捜していた仇に会ったときのようにどうしてもそのまま見過ごすことができない。老舗和菓子店の高級なお菓子、外国ブランドの高価な物などはもちろん、大手菓子メーカーが秋に必ず出す「季節限定栗味」のクッキーや煎餅でも同じだ。堂々と「栗」と表示してあるからには「その挑戦、受けて立とう」とついつい買ってしまうのだ。
それはなぜか。ちゃんと理由がある。
小さい頃、茹で栗はうれしいおやつだった。茹で上がった大きな栗を母が半分に切ってくれて、それを小さなスプーンで食べるのだが、大人だってどんなに気をつけていてもボロボロこぼしてしまうものだ。そしてそのこぼれたカスの始末はなかなかやっかいだ。
知らずに踏んづけると畳の目に入り込んでしまうし、運悪く畳の縁に付こうものなら白くなって、いくら濡れ雑巾でこすってもスッキリと元通りにはならない。
これを恐れた母は、茹で栗を食べさせるときには必ず新聞紙を敷いた上に私達を座らせ、そこから出ないように監視していた。食べ終わってもすぐに自由にはしてくれず、服の上に落ちているであろう栗のカスをその新聞紙に落としてからでないとそこから出ることを許さなかった。
食べている最中も母の厳しい目は私達から離れず、「ほら、こぼれた」「動かないで」と容赦がない。新聞紙のガソゴソとした座り心地も不快で、ある時、幼い私はとうとう堪忍袋の緒が切れて叫んだのだ。
「こんなにおいしいものを食べているのにごちゃごちゃ言わないで!せっかくのおいしいもの、ゆっくり食べさせて!」
それ以来、「母の厳しい監視も小言もなしで、おまけに新聞紙の上で食べなくてもいい」栗のお菓子は、私の切実な願いを叶えてくれるものになったのだ。
カスをこぼすことなく一粒を丸々口に入れることができる天津甘栗、ケーキは必ずモンブラン、栗蒸し羊羹にマロングラッセ、時には母娘3人でゆっくり味わいながら、やっぱり子供の時の仇を取っているのかもしれないな、と思う。
作品2.「正月の戦い」 さゆまり (大阪府)
栗好きを自覚したのはいつの頃だったのだろうか?
今の私は「栗」という字を見るだけで心踊る。これは一種の栗中毒であると認識している。
「栗」の入った苗字でさえ、素敵で羨ましいと思ってしまう。
それはさて置き、その大好きな栗のなかでも不動のナンバーワンは、母の作った栗きんとんであった。
いまでこそ栗きんとんは身近な存在?となったが、私の小さな頃はおせち料理でしかお目にかかれなかった。
なので毎年お正月が来るのを楽しみにしていた。
母の作る栗きんとんはさつま芋餡と栗の割合が8:2くらいで、ほとんどがさつまこれ芋餡だ。
その餡の中から栗を見つけた時のなんとも言えない高揚感。
がしかし、私は4人兄弟で両親との6人家族。
そして厳格な父は、躾に厳しかった。
箸の持ち方が悪いと容赦なく手を弾かれまた、食事中机に肘をついた日には「食べるなー」となる。
なので好きなものばかり食べるわけにもいかず、栗きんとんに箸をつけ、栗が当たればいいがなかなか当たらず、兄弟に先を越されてしまう事もある。
それは正に戦いであった。
これを逃すと、一年後までお預けになってしまうのだから。
そんな私は20歳過ぎで親元を離れ、すぐに結婚し4人の子宝に恵まれた。
色々な事情があり里帰り出産はせず、お正月に帰省した事もなかった。
ただがむしゃらに働き、子育てに追われていた。
おせち料理は毎年作っていたが、主導権は私にあったので、栗きんとんとの戦いは無くなっていた。
好きなだけ「栗」を食べられたのだ。
そんな中状況が変化し、親元を離れから初めてお正月に帰省することになった。
4人の子供を連れて…
そして母の作ったおせち料理とお雑煮を、何気なく食べていた。
すると20年間忘れていたあの高揚感がふと蘇り、思いがけず泣きそうになった。
「あー。やはり母の作った栗きんとんが一番好きだな」と。
作品3.「さくら先生」 山本 さくら (福井県)
さくら先生。結婚してすぐ夫からそう呼ばれるようになった。「インフル注意報が発令されました。手洗いうがいは、さらに丁寧にしましょう。」「イチゴは果物でしょうか、野菜でしょうか。」どうやら、ひとこと一言が先生口調らしい。
先日、夫が日課にしているランニングに同行すると張り切って用意を始めた。年に数回こういう日がある。気まぐれに健康に目覚めるのも、さくら先生らしい一面である。
「急に走ると体に負担がかかるから、まずはウォーキングから。」と仕切り、歩き始めて5分。足全体が痒くなる。「急に血の巡りが良くなって、痒くなるんだって。日ごろの運動不足が原因らしいよ。」かれこれ100回は語った。「もうちょっと待ってね。思いっきり掻いたら痒いのを通り越せるから。」こちらは、さくら先生の経験則。痒さが落ち着いた後の皮膚は真っ赤なので、決して真似しないでほしい。
まだ一歩も走っていない夫に心の中で断りを入れ、存分に掻ける所を探し移動し始めた。歩きながら掻けることは、この道ン十年の成せる技と、さくら先生少々得意気である。大きなダンプが数台停まる駐車場が見つかった。ダンプの間に身を寄せようと足を速める。
すると、目の前に大きな毬栗がぼとぼとと落ちているではないか。一瞬にして痒さが収まる。夫を呼び、栗が入っているかどうかを確かめさせる。自分では調べようとはしない。大先生である。
「栗は、中身だけ拾います。」「小さいころ、パパと栗拾いに行ったことがあって、知っているんだ。」へえ~、と頷く夫。「でも、どうやって?」生徒歴18年、夫の質問には無駄がない。「いい質問ですね。靴で踏んで皮をむくように毬を取り除きます。どうぞ!」えっ、とためらう夫に、「まず、やる。」促すさくら先生。次の瞬間「痛っ!」という予想外の声が。「なんで?」靴の裏を見ると、栗の棘が何本も刺さっている。痛がる夫に背を向け、肩を震わせ笑う先生。悪魔先生である。どうやら靴底の一部が、通気性を良くするためメッシュになっていたらしい。「わざとじゃない、ごめん。」と先生、内心では詫びている。
棘を手で一本ずつ取り、シューズと靴下を脱いで足の裏を見てみる。先生は、手を貸さない。見守るのが先生だ。あぁ、ブツブツ赤い。「大丈夫、私の太ももより赤くない。帰ろう。」そう言って、家に向かって歩き始める。無事に夫を連れて帰らねばという使命感からか、帰りは痒さの「か」も感じず帰ることができた。手中に、つややかな栗を一粒握りしめて。
作品4.「チイキをつなげるケーキ。」 もつにこみ(東京都)
モンブランのおかげで、こんなに人を感じることになるなんて、意外だった。
僕は、栗好きで、ケーキ好き。つまり、モンブラン(以下、モン)が大好きだ。
モンが好き。好きなケーキはモン。モンの季節が来た。
モンモン言い続けていたら、妻が呆れて、友人に笑い話として披露してしまった。
すると、あろうことか、市内にあるケーキ屋さんのモンを集めて、
地域の方々と食べ比べよう!というイベントが開催されることになってしまった。
当日を迎えて、ひとりの参加者のつもりで向かうと、実は運営側として数えられていて、
慌ただしい準備ののち、必死にモンを4等分するという作業に没頭することになった。
企画の発案者でしょ、と言われれば反対はできないし、
なにより、このイベントを誰よりも楽しみにしていたという自覚もある。
集めたモンは、市内7店の力作たち。胃袋の都合から、切り分けて食べ比べることになっていた。
集まった方々は、まさに老若男女。
口を揃えて「モンが好きなんです」という参加者の皆さんは、お客様ではなく同志たち。
年齢関係なく、好きなものを分かち合えるのは、とても幸せなことだ。
それぞれの店のモンを並べると、意外にも、似ている外観のケーキはなかった。
ショートケーキには決まったスタイルがあるようだけど、モンは違っていた。
クリームの色、盛り付け方、栗が乗っているか、台は何か。お店の工夫や愛が、すべてのモンから感じられた。
メッセージもいただき、読み上げられるたびに、作り手の熱い想いが伝わってきた。
イベントの前半は、モンを4等分する作業に没頭していたけれど、
試食しているときの表情を見かけたり、コメントが聞こえるたびに、嬉しくなった。
「それぞれ違いはあるけれど、モンって美味しいケーキなんだ」と、
あらためて思いを馳せる時間を過ごせたことは、とても幸せだった。
イベントの帰り道、心地よい疲れを感じながら気がついたことがあった。
モンブランのおかげで、こんなに人を感じることになるなんて意外だった。
地域の皆さん、作り手のお店、企画してくれた妻と友人、さらには消費者としての僕。
イベントの趣旨として1位を決めた。
でも、どの店も食べた人を幸せにできる、また食べたいと思えるケーキだった。
「新たな魅力に気付いた。」
と言ってくださった参加者の嬉しそうな顔を思い出しながら、この話を書いた。
ありがとう、モンブラン。
大好きだよ、モンブラン。
エッセイ部門賞
作品5.「笑顔の香り」 竹外 眞由美(長崎県)
亡くなった母は、とても料理上手な人だった。
わたしは四人姉妹だが、姉妹それぞれに懐かしく憶い出す母の味がある。
一番上の姉は、遠足に持たせてくれていた海苔巻こそがそうだと言う。
二番目の姉は、お煮しめ料理の翌日、余った具材で作ってくれる混ぜごはんこそがそうだと言い切る。
三番目の姉は、運動会に持ってきてくれた御重を開いた瞬間手を出さずにはいられないほど、母の稲荷寿司が好きなのだと言う。
四番目のわたしにとっての母の味は、断然、栗ごはんだ。
子どもの頃のわたしは、そもそも栗が大嫌いだった。
栗を剥いていると時々出てくる虫が大嫌いで、その不幸な出会いを避けるため、いつしか栗そのものを食べなくなっていた。
そんなわたしに栗を食べさせるため、母は下ごしらえに時間を掛け、一目で虫がいないと分かるよう二つ割にしたもので栗ごはんを作ってくれていた。
栗(虫)嫌いなわたしが唯一、ウマウマと栗を口にすることが出来るのは、母が栗ごはんを作ってくれた時だけだった。
しかし、わたしが「栗ごはんを好き」だと言えるようになるには、もうひとつ越えなければならない難関があった。
白米に甘いものを合わせて食べることができなかったのだ。
栗ごはんを食べる時も、まず茶碗の中から栗をほじくり出し、おかずと一緒にごはんを食べきったあと、おもむろに栗をほおばるという順番だった。
そんなわたしを見て、ある時、母がこう言った。
「だまされたと思って栗とごはんを一緒に、ゆっくり噛んでごらん。ごはんの甘さと栗の甘さが合わさって、両方の香りが鼻の奥で感じられるから」
ほら、とでも言うように、茶碗をわたしに差し出した。
嫌いなことを強いられる時多くの子どもがそうするように、わたしも眉間に皺を寄せ、それこそ苦虫を噛み潰すような表情で、栗とごはんをそっと口に運んだ。
もぐ…もぐ…。
「…あ。」
「ね? 香りが分かるでしょう?」
母の言う通りだった。
新米の芳しい香りと、栗の何とも言えない甘い香り、その双方が鼻の奥でそれぞれに香ってきた。
「美味しい!」
「ふふっ、良かった」
母はにっこり笑って、自分の茶碗から栗を三粒ほど、わたしの茶碗に乗せてくれた。
大人になったいま、その母の栗ごはんを、自分で作る。
渋皮を剥いていると、家族六人分の栗を下ごしらえしていた当時の母の苦労がよく分かる。
そして土鍋に炊き上がった栗ごはんの最初の一口を食べた時、懐かしい、あの母の笑顔を思い出すのだ。